こんにちは!りんぐるです。
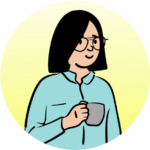
私は、2021年10月に受験した宅建に一発合格し、人生が変わりました!
「法令上の制限」は数字やルールが多くて大変…
この分野は覚える量がすごく多くて、とっても大変ですよね。
でも、ポイントを押さえれば覚えやすくなります!私なりの解釈のしかたをお伝えします。
「まちづくり」がこの分野のイメージ!
法令上の制限は「まちづくり」が大きなテーマ!

行政が「このエリアはこんなまちにしよう」と考え、家を建てるエリアややお店を誘致するエリアなど、エリアごとに法律を決めていきます。
つまりは、自分が市の開発担当者だったら?という目線で考えることがこの分野の理解に繋がります!
自分が住んでいるエリアが、どの用途地域なのか?をご自身の自治体のホームページで調べてみると、より身近に感じますよ!
「どうしてその制限が必要なのか」を考える
自分が街づくりをしようとしたら、ルールを決めないと、自分勝手に建物を建てられたら困りますよね?なので、それぞれの法律がどうして必要になったのか、を考えましょう。
- 都市計画法 → 市全体のバランスをとって、住みやすい街にしよう
- 建築基準法 → 火事などが発生したときに、不都合がおこらない建物づくりをしよう
- 宅地造成等規制法 → がけ崩れで災害が起きないようにしよう
- 農地法 → 農業を守って、安定的に食料を供給しよう
- 国土利用計画法 → 土地の価格が高騰しないようにしよう
- 土地区画整理法 → 古い町並みをキレイに整地しよう
このように、それぞれの法律ができた背景があります。これを頭においておくと、このあとの勉強がスッと腑に落ちるように理解できるようになります。
なぜ?と疑問に思い、具体例を思い浮かべる
勉強や過去問をしながら、具体的なイメージをしてみると良いでしょう。

住宅同士がぎゅうぎゅうに建築されていると、日光があたらない家になってしまいます。さらに火事がおこったときすぐ隣の家に火が燃え移ってしまいますよね。なので、建蔽率や容積率で建物のサイズを決めています。
道路の幅が狭いと、火事がおこったときに消防車が通れないですよね。なので建築基準法で道路幅4m以上と決められているんです。
…とこんな具合に、なぜ?を考えるとこのルールを決めた理由が見えてきます!
図を描いて整理する
文章だけではなかなか理解しづらい分野ですが、図を書くことで、イメージがつきやすくなります!
完璧を目指さず、よく出る数字&ルールを優先して覚える
専門用語が多い分野ですが、実は過去問で問われた内容が出題方法を変えて何度も登場することがよくあります!
過去問を繰り返し解くことで、どの範囲が頻出かわかってくるので、そこを重点的にくりかえし覚えましょう!
ゴロあわせ&歌で覚える
放れ上の制限は暗記が多くて本当に大変!覚えきれません!
でもYouTubeで替え歌を出してくださっている棚田行政書士の歌で、しっかりと覚えられます!
是非何度も何度も聞いて、歌にのせて過去問を解いてみてください!まさに神曲です!
深入りすると、時間が無駄になる
最初にイメージすることが大事、とお伝えしましたが、法令上の制限は深入り不要です。
ここは覚える項目がいっぱいありすぎて、深く考えると時間と脳のリソースがものすごく無駄になります。
「なるほど、こういう理由でこの法律ができたんだね。よし過去問やろう」ぐらいの状態で、都市計画法の表と過去問を照らし合わせながら解いていったほうが、効率が良くイメージがつかみやすいかと思います。
まとめ
法令上の制限では、用語の意味や定義、数字などが問われますが、過去問で頻出される問題は限られているという特徴があると思います。
ここで高得点を目指ざせると、ほかの受験生と差別化をはかれます!
ここでなんとか踏ん張って、過去問をなんども繰り返し、問題に慣れて得点できるようにがんばりましょう!



コメント